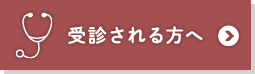- ホーム>
- がん・疾患情報サービス>
- がんおよび各種疾患についての説明>
- 泌尿器がん: 膀胱がん
泌尿器がん: 膀胱がん
膀胱がんとは
膀胱は骨盤内にある臓器で、腎臓でつくられた尿が腎盂、尿管を経由して運ばれた後に、一時的に貯留する一種の袋の役割を持っています。膀胱がたまった尿で伸展されると、それを尿意として感じ、筋肉が収縮することによって排尿して、膀胱より尿を出しきるといった働きがあります。膀胱の表面は移行上皮という名前の上皮でおおわれ、伸縮性に富むことが特徴的です。膀胱癌は、この移行上皮ががん化することによって引きおこされ、組織学的には移行上皮がんが全体の90%を占めています。
膀胱癌の頻度は、人口10万人あたり毎年約17人発生し、それほど多いがんではありませんが、年々若干増加の傾向にあります。男女比では女性より男性に多く、女性の約3倍多いといわれています。多くは40歳以上に発生しますが、若年者にもときにみられます。
当院では1年間に80人前後、新しい膀胱癌の方が来院され治療を受けています。
膀胱がんの原因としては、喫煙者は、非喫煙者の2~3倍の割合で膀胱がんになりやすいといわれています。また、化学薬品や染料を扱う職業にも発症率が高いことが知られています。
膀胱癌は、大きく分けて3つのタイプがあります。
1.表在性乳頭状膀胱癌
肉眼的に、ちょうどカリフラワーか、いそぎんちゃくのように表面がぶつぶつとなっているかたちをしたがん(乳頭癌)で、膀胱の内腔に向かって突出しています。しかし、がんの病巣は、膀胱の粘膜にとどまっていることが多く、転移や浸潤をしないものです。
2. 浸潤性膀胱癌
1.のタイプのがんと異なり、がんの表面は比較的スムーズ(非乳頭がん)で、こぶのように盛り上がったものから、膀胱粘膜下に進展して粘膜がむくんで見えるものまでさまざまです。このがんは、膀胱を貫いて、壁外の組織へ浸潤しやすく、また転移しやすい特徴があります。
3. 上皮内癌
膀胱の表面には、ほとんど隆起した病変を生じませんが、膀胱粘膜壁に沿って悪性度の高いがん細胞が存在している状態です。初期のがんではありますが、無治療でいると浸潤性のがんになっていきます。
症状
1)肉眼的血尿
膀胱癌の初発症状として、最も多く認められる症状です。膀胱炎と違って、痛みは伴わないことが一般的です。数日経過すると突然血尿が止まってしまう場合がありますが、心配ないということは決してありません。しかし、血尿があるからといって、必ずしも膀胱がんをはじめとする尿路系のがんがあるとも限りません。
2)排尿痛、頻尿、排尿困難
ときに初発症状が排尿時痛や下腹部の痛みで出現する場合があります。この症状は膀胱炎と非常に類似していますが、抗生剤を服用してもなかなか治らないことが特徴です。
診断
膀胱癌は、膀胱鏡を行うことによってほとんどが診断できます。尿に癌細胞が落ちているかを調べる尿細胞診も有効な検査です。しかし、小さな乳頭状の癌では、尿細胞診ではっきり癌細胞と断定できないことがあります。ひとたび膀胱癌が見つかった場合には、他のがんと同様に、CTや胸部X線撮影、腹部のエコーなどでその拡がりと転移の有無を調べる必要があります。しかし、乳頭状のがんは転移したり局所で浸潤するようなことはまれですので、必ずしも全身の転移の検索は必要ではありません。また、膀胱にがんが見つかった場合、同じ移行上皮でおおわれている腎盂・尿管にも同様のがんが見つかる場合がありますので、腎盂・尿管の病変の有無をチェックする排泄性腎盂造影検査を行う必要があります。がんの確定的な診断には、腰椎麻酔下に膀胱粘膜生検が必要です。
治療方針・治療法について
(A)表在性膀胱癌の治療
[ 原則として経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TURBT) にて治療します ]
腫瘍の悪性度が低く、多発傾向の乏しい場合、TURBTによる単独治療とし、通常、補助療法は行いません。多発性、繰り返す再発の時には、BCGまたは抗がん剤の膀胱内注入療法を併用します。
膀胱上皮内癌の方はBCG注入療法が標準治療になります。
- 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)について
表在性の膀胱癌ではこの術式が適応となります。膀胱内に特殊な膀胱鏡を入れて内視鏡で確認しながら、電気メスでがん組織を切除する方法です。今後の治療方針を決めるために膀胱の筋層まで切除します。手術時間は1時間程度です。手術後膀胱を安静に保つ目的で、自然に尿を体外へ誘導するために、膀胱内に管(カテーテル)を留置します。通常1 - 3日目に抜去します。浸潤度の高いがんでは、完全に切除することが困難で、この治療法では不十分です。
表在性膀胱癌では異型度によっては、1カ月後に2回目のTURBTを施行し、癌の残存を確認し、浸潤性癌の見逃しがないことを確認することもあります。
- TURBTの合併症
1) 後出血
術後3週間以内に、力んだり、尿を膀胱内にため過ぎたり、アルコールや刺激物の取りすぎなどにより、切除部位から出血することがあります。
出血したら数日間、尿道カテーテルを再留置し、膀胱を安静に保つことにより多くは対処できますが、まれに止血のため再手術が必要になる場合もあります。
2) 膀胱穿孔
切除した組織診断により今後の治療方針が決定するため深く組織を採取する必要があり、膀胱に穴が空いてしまう可能性があります。小さい穴ならカテーテルを1週間前後留置するだけで治癒しますが、大きな穴や腹腔内への穴の場合には腹膜炎などの重大な合併症が生じる可能性もあり、緊急に全身麻酔に切り替えて、開腹して漏れた尿を外へ出し、膀胱を縫合する手術が必要になります。
3) TURBT後症候群
TURBTという手術は、膀胱内を潅流液で洗いながら行いますが、その潅流液が出血部位から血液中に多量に吸収されると血液がうすまり(水中毒)、呼吸困難や胸部不快感、ショック症状を起こすことがあります。利尿剤や副腎皮質ホルモンの投与、適正な輸液などを行います。
4) 前立腺炎、精巣上体炎、腎盂腎炎
細菌感染が起こると、高熱や痛みが生じます。抗生物質の投与などが必要です。
5) 尿道狭窄
手術用内視鏡器具の挿入による刺激のため尿道狭窄が生じることがあります。尿道拡張(ブジー)もしくは内尿道切開術で対処します。
- BCG注入療法の副作用について
1) 膀胱刺激症状
尿の回数が多くなったり、排尿時の痛みや血尿がみられます。程度が強い場合は、治療を中断し、痛み止めなどを使用します。
2) 萎縮膀胱
膀胱が不可逆的に小さくなると、激しい頻尿と下腹痛に悩まされます。 膀胱刺激症状を我慢して無理に治療を継続した場合などに起こります。尿路変向術が必要になることもあります。
3) 発熱、倦怠感、敗血症、肝障害、アレルギー(ショック)など
BCG注入療法ではこのような危険な副作用がみられることがあります。 体力が低下し、免疫状態の低い方、あるいは重度な結核感染の既往のある方にはBCGは禁忌です。症状がひどい場合は、抗結核薬や副腎皮質ホルモンによる治療が必要です。
※抗癌剤の膀胱内注入療法でも上記1、2、3を認めることはありますが、副作用の頻度は低いのですが、効果も少ないようです。
- 膀胱内再発および外来通院について
表在性の膀胱がんでは、致命的になることはまれです。ただし、膀胱癌は膀胱内に多発すること、何度も再発することが特徴です。当院での初回5年再発率は55.8%ですが、2回目、3回目、4回目の再発では72.4%, 63.2%, 72.6% と再発率は高くなります。膀胱内再発が見られたら再びTURBTを行うことが多いのですが、場合によってはBCGや抗がん剤の膀胱内注入療法を行います。また再発を繰り返すうちに、浸潤性の癌へと癌の性質が変化することがあります。注入療法に抵抗性を示し、腫瘍が広範囲に再発したり、尿道や下部尿管に進展したり、浸潤がんに進行したりした場合は膀胱全摘除術を考慮します。
TURBTの後は、担当医の指示にしたがって定期的に5年ぐらいは外来に通院し、膀胱鏡や尿の細胞診でチェックしてもらう必要があります。5年以降は1年に1回来院して頂くこともあります。腎臓(腎盂)・尿管などの上部尿路腫瘍発生の心配もありますので、腎盂造影・CTなどの検査をすることもあります。
(B)浸潤性膀胱癌の治療について
1) 膀胱全摘術 ± 抗がん剤療法の併用(術前・術後) ± 放射線治療 + 尿路変更術
2) 抗がん剤治療(動脈内または静脈内)後に、放射線治療または膀胱部分切除
癌の大きさが3~4cm以下の浸潤性の膀胱癌を対象にしています。
患者さんの生活の質の改善を目指し、試みられています。
現段階では1) の膀胱全摘術が標準的治療です。この治療効果を向上させるため、手術前後に全身化学療法や動注化学療法を施行することもありますが、その効果については一定の見解を得ていません。
膀胱全摘を希望しない方に対して、2) に示しますように、抗癌剤化学療法と膀胱部分切除術または放射線併用による治療効果の改善の可能性が現在探られています。たとえば抗癌剤(動脈内と、静脈内)を3サイクル投与した後、放射線治療または膀胱部分切除により、短期的に腫瘍が完全に消失する率は60 - 80%とも報告されています。しかし再発の可能性など長期的成績は未だ定まっていません。
- 膀胱全摘除術について
がんの浸潤度が高く、TURBTで不十分な時にはこの手術が必要です。全身麻酔を行い、骨盤内のリンパ節の摘出(骨盤内リンパ節郭清)と膀胱の摘出を行い、男性では前立腺、精嚢(せいのう)、女性では時に子宮を摘出します。また、尿道も摘除することがあります。男性では、手術後にインポテンツになる可能性が高いのですが、術式によっては、それを防ぐことは可能なこともまれにあります。ただし、前立腺、精嚢をとってしまうため、射精は全く不可能になります。
膀胱を摘出した後は、「尿をためておく袋」がなくなりますので、何らかの尿路の再建が必要となります。これを尿路変向(変更)術と呼びますが、下に5つの方法を示しました。現在、当院ではおもに回腸導管とネオブラダー(人工膀胱)を採用しています。
尿路変向法のいろいろ

A) 回腸導管造設術
左右の尿管を遊離した小腸の一部に植え込んで、その回腸の先を皮膚に出す方法です。皮膚から飛び出した回腸の部分をストーマと呼びますが、ストーマには尿をためる袋をつけておかなければなりません。この方法は、かなり以前から行われている最もオーソドックスな方法で合併症が少ないことが特徴です。しかし、たえず尿がストーマから流れ出ているので、常時袋をつけていなければならないわずらわしさがあります。
B) 自排尿型新膀胱造設術(ネオブラダー)
腸を使って人工的な尿をためる袋をつくることは導尿型新膀胱造設術と同じですが、その出口を尿道につなぐ方法です。この方法はストーマがなく、尿道から尿が出せることが大きな特徴です。しかし、膀胱がんは尿道にがんが再発することがあるため、尿道に再発する危険性が高い場合は適応となりません。排尿機能は本来の膀胱のようにはいかず、排尿困難や尿失禁が多少とも認められます。
- 放射線療法について
放射線にはがん細胞を死滅させる効果があるので、がんを治すため、またはがんにより引きおこされる症状をコントロールするために使われます。放射線治療の適応となるものは基本的に浸潤性の膀胱がんです。膀胱の摘出手術では尿路変更が必要となるデメリットがあるため、あえて放射線治療や、放射線治療に化学療法をあわせて治療し、膀胱を温存することもあります。しかし、病巣周囲の正常組織にも放射線の影響が及ぶため、膀胱が萎縮し尿が近くなったり、直腸より出血したり、皮膚のただれが生じることがあります。また、転移した病変のコントロールに放射線治療が選択されることがあります。
- 抗がん剤による化学療法について
転移のある進行した膀胱がんは化学療法の対象になります。使用する抗がん剤は、通常2種類以上です。GC療法(ゲムシタビン、シスプラチン)が、現在膀胱癌の治療に最もよく行われる化学療法です。治療中は副作用として、吐き気、食欲不振、白血球減少、血小板減少、貧血、口内炎などがおきることがあります。また、転移がない膀胱がんでも、筋層以上に浸潤している時には、術後の再発や、遠隔転移の予防に術前、あるいは術後に化学療法を追加する場合があります。GC療法が無効な時にはM-VAC療法(メソトレキセート、ビンブラスチン、アドリアマイシンあるいはその誘導体、シスプラチンの4剤の組み合わせの治療)またはゲムシタビン+パクリタキセル療法が行なわれます。また近年新しい抗がん剤を用いる治療も注目されています。
- 浸潤性膀胱癌治療の副作用について
1) 外科療法
膀胱全摘術は全身麻酔で約5 - 8時間位かかり(ネオブラダー作製の時はさらに時間が延長するときもあります)、術後最低3週間以上の入院が必要です。手術の早期合併症として、出血による輸血の可能性、リンパ節郭清(リンパ節を切除すること)後のリンパ液の貯留と炎症および足のむくみ、縫合不全(傷が開く、腸管と尿管の吻合部から尿が漏れる、腸と腸の吻合部から便が漏れる)、腸閉塞、周囲臓器(直腸、結腸、小腸)損傷などがあります。
出血に対しては輸血が必要になるときがありますが、輸血にはウイルス感染や免疫反応などの危険性が多少あります。それを避ける方法として、あらかじめ自分の血液を採血・貯蔵しておき、手術の際に体に戻す自己血貯血法という方法があります。2-3週間前後の準備期間が必要です。縫合不全に対しては、消毒と栄養状態の改善に務めることで対処します。時によっては開腹術が必要になります。腸閉塞では、原因により異なりますが、保存的に点滴や胃の持続吸引などにて対処しますが、再開腹術が必要になることもあります。周囲臓器損傷に対しては人工肛門などが必要になることもまれにあります。
手術中・直後の全身に起きる大きな合併症として、心筋梗塞・肺梗塞・脳梗塞・脳出血が0.5%程度発生するといわれています。致命的な合併症で一度起きてしまうと危険な状況に陥る可能性もあります。
2) 化学療法
使用する抗がん剤の種類によって異なり、個人差もありますが、治療中の主な副作用は骨髄毒性(貧血、白血球減少による感染、血小板低下による出血傾向)、吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢、手足のしびれ、肝機能障害、腎障害、脱毛、疲労感など、その他予期せぬ副作用もみられることもあります。原則として、これらは抗がん剤投与後2~3週間で改善するため対症療法を行います。強い白血球減少に対しては感染を防ぐために白血球増殖因子(血液を産生する骨髄に作用し、白血球を短期間で多くつくらせる薬)を投与します。
3) 放射線療法
放射線の有害事象には放射線治療中に生じてくるもの(早期有害事象)と治療終了後数ヶ月以上経過してから生じてくるもの(晩期有害事象)とがあります。残念ながらこれらの障害の出方や強さをあらかじめ予測する方法はいまのところありません。
早期有害事象は全身的なものと局所的なものがあります。全身的なものとしては、倦怠感、食欲不振、吐気、血液の変化(白血球、血小板減少など)などがあげられます。局所的な早期有害事象は半数以上の方に生じますが、その症状の出方や強さはかなり個人差があります。局所の早期有害事象は放射線による粘膜炎の症状として出てきます。症状がでてくるのは治療開始後2~3週目くらいが一般的です。
症状が強い時には、薬剤を使って症状を緩和させます。それでも症状が緩和せず、強くなる場合には、放射線治療を一時休むことになりますが放射線治療を休止するまでに強い症状の出る方は1~2%くらいです。この早期有害事象は一般的には、治療が終了してから2~4週くらいで徐々に治まってきます。
晩期有害事象は放射線治療終了後数ヶ月以降に生じる副作用です。放射線をかけた場所に生じてきます。毛細血管が放射線をかけたために詰まって、血流が悪くなるのが原因の大部分をしめていると考えられています。軽症なら経過観察のみ、または対症療法で様子をみていきますが、重症になると輸血や手術が必要になることもあります。放射線による晩期有害事象は改善するまでに時間がかかるのが特徴で、半年から数年かかることもあります。
放射線治療を受けることで発癌性について心配される方がいらっしゃると思います。放射線治療で誘発される癌の発生時期は、白血病では5年以内に発症することも報告されていますが、固形腫瘍では10年以上後から出てくるとされています。
浸潤性膀胱癌の治療成績・生存率
浸潤性膀胱がんで膀胱全摘を行った場合、当院の5年生存率はstageⅠ(n=36)では89.7%、stage Ⅱ(n=72)は71.3%、stage Ⅲ(n=79)は58.9%、stage Ⅳ(n=75)は16.9%です。リンパ節転移・骨盤壁・前立腺浸潤を認めるstage Ⅳでは術前・術後の抗癌剤投与や放射線治療を含めた集学的治療が必要と思われます。
近年、化学療法なども進歩してきており、今後これらの成績も向上していくものと思われます。また、これらの数値はたくさんの患者さんの平均的な統計学的数値であり、あくまでその傾向を示すもので、個々の患者さんにあてはまるものではありません。