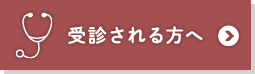- ホーム>
- 施設のご案内>
- 医療従事者向け図書室 >
- 県立がんセンター新潟病院医誌 >
- 第37巻第1号 1998年1月
第37巻第1号 1998年1月
目次
総説
- 脳と免疫:1
吉田誠一
特集 がん化学療法の現状Part2
- 小細胞肺癌における化学療法:6
上原裕子、森山寛史、横山 晶、栗田 雄 - 進行食道癌に対する化学療法:13
秋山修宏、船越和博、加藤俊幸、斉藤征史、小越和栄、田中乙雄 - 小児がん化学療法の現状と問題:19
浅見恵子 - 精巣腫瘍の化学療法:27
小松原秀一、渡辺 学、北村康男、内藤雅晃 - 卵巣癌の化学療法:31
笹川 基、菊池真理子、遠藤道仁、本間 滋、高橋 威 - 骨軟部肉腫に対する化学療法の現状:37
守田哲郎 - 乳癌の補助化学療法:43
佐野宗明、牧野春彦、張 高明
臨床経験
- 早期胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の現況:52
梨本 篤、土屋嘉昭、秋山修宏 - 当院における迅速組織診断の現状:58
根本啓一、本間慶一、村山 守、渡辺芳明、桜井友子、西村広栄、字佐見公一、小林由美子、佐藤由美、泉田佳織里、山口栄子、島津ハナ - 大腸内視鏡26年の歩み:63
斎藤征史、加藤俊幸、兎澤晴彦、古谷正伸、船越和博、秋山修宏、小越和栄
要旨
脳と免疫
Brain and Immune System
吉田誠一
Seiichi YOSHIDA
ラットの破壊実験より,前視床下部が胸線におけるT細胞の機能分化やMHC抗原を介した抗原認識機構などに関与しており,視床下部一下垂体−副腎系とサイトカイン系との間にフィードバック機構が成立していると考えられた。悪性脳腫瘍患者においては,腫瘍組織から能動的な免疫抑制が働いており,BRMの局所投与により著明なTリンパ球とマクロファージの浸潤を認めた。そこで,患者リンパ球からLAK細胞を誘導し,脳腫瘍の摘出腔に投与すると有効例も確認でき,維持療法として有用と考えられた。遺伝子解析からは,腫瘍細胞から産生されるIL-8が腫瘍の自律的増殖に働く事が示唆され,アンチセンス分子を用いた治療法やサイトカイン補充療法の可能性などが期待され,神経免疫調節系の全体像を把握した理想的な治療法の開発が望まれる。
小細胞肺癌における化学療法
Chemotherapy for Sma1l Cell Lung Cancer
上原裕子、森山寛史、横山 晶、栗田雄三
Hiroko UEHARA,Hiroshi MORIYAMA,Akira YOKOYAMA and Yuzo KURITA
近年,当科で行ってきた小細胞肺癌の治療に関する臨床試験の成績を報告するとともに,現在のコンセンサスについても述べる。進展型の標準的治療はcisplatinとVP-16の併用療法あるいはcyclophosphamide,adriamycin.vincristineとの交替療法4〜6コースとされる。大量療法,weekIy intensive chemotherapyなどの優位性は検証されていない。限局型では,化学療法単独よりも胸部放射線併用により延命効果があり,治療早期に,化学療法と同時に併用する方法が標準的である。ただし,標準的治療では,治癒に至る症例が少なく,さらに局所制御の改善・全身的治療の増強が必要である。当科では,導入療法後の外科的切除,また,末梢血幹細胞移植併用大量化学療法を試みており,この成績についても報告する。
進行食道癌に対する化学療法
Chemotherapy for Advanced Esophageal Cancer
秋山修宏、船越和博、加藤俊幸、斉藤征史、小越和栄、田中乙雄
Nobuhiro AKIYAMA,Kazuhiro HUNAKOSHI,Toshiyuki KATO,Yukihumi SAITO,
Kazuei OGOSHI and Otuo TANAKA
我々は,切除不能の進行食道癌症例9例にCis-platin(CDDP),5-Fluorouracil(5FU)併用化学療法(FP療法)を行い,3例にFP療法に同時併用放射線療法を組み合わせた治療を試みたのでその成績を報告する。FP療法9例中CR1例,PR5例,NC3例,奏効率6例/9例(66.7%)であった。放射線治療同時併用FP療法3例では2例にPRが得られ,奏効率66.7%であった。白血球減少,悪心・嘔吐が主な副作用であったが,Grade 3以上の重篤な有害事象は認めなかった。disease free survivalは6か月49.0%,1年29.0%,2年29.0%であった。overall survivalは6か月は81.0%,1年35.7%,2年35.7%であり,50%生存期間は8.2か月であった。化学療法でCRとなった症例,化学療法後臨床病期の改善を認め外科手術を行ったもの,放射線化学療法が著効を示した症例では長期予後が得られた。外科手術,放射線療法,化学療法を組み合わせた集約的治療を行い治療成績を改善する事,症例数を増やし条件をそろえた検討を行う事が必要と思われた。
小児がん化学療法の現状と問題
Current Chemotherapy of Cancer in Children
浅見恵子
Keiko ASAMI
小児がんは近年の診断技術の進歩と”total cell kill theory”に基づいた強力な化学療法を中心とした治療により,息者の約60%が完治するようになっている。しかしその一方,腎,肺,心臓,聴力,神経,生殖機能障害などの晩期障害,社会的不適応,二次癌発症などが間題になってきている。当科の白血病,悪性リンパ腫などの治療成績はおおむね全国レベルに近く,治療終了5年以上経過した18歳以上の症例は50例に達している。
このうち5人は既に結婚し,うち4人に正常な6人の子供が誕生している。また現在でも治療困難な進行神経芽細胞腫,横紋筋肉腫などに対しては新たなプロトコールによる治療が試みられており,今後,一層の治療成績の向上が期待されている。
精巣腫瘍の化学療法
Chemotherapy for Testicular Cancer
小松原秀一、渡辺 学、北村康男、内藤雅晃
Shuichi KOMATSUBARA,Manabu WATANABE,Yasuo KITAMURA and Masaaki NAITO
精巣腫瘍は化学療法が有効で,転移癌も治癒し得る。現在,非セミノーマ精巣腫瘍では一部の難治例に対する治療法の確立と,予後良好群に対する過不足のない治療法の模索が続けられている。予後良好群には,BEP(CDDP,VP-16,BLM)3コースないし,EP(CDDP,VP-16)4コースが,予後不良群には,BEP療法4コースが標準の治療法と考えられている。救済療法として,VIP(CDDP,IFM,VP-16ないしVBL)があるが効果は不十分で,高用量化学療法(PBSCT支持)に期待が寄せられている。セミノーマは放射線,化学療法ともに有効である。当院では精巣および性腺外胚細胞腫瘍19例(観察期間が5年以上)にBEPと残存腫瘍の切除を行った。予後良好群には主として通常量を,不良群,再発例には主にCDDPを増量して投与し、l9例中17例(89.5%)が治癒した。
卵巣癌の化学療法
Chemotherapy for Ovarian Cancer
笹川 基、菊池真理子、遠藤道仁、本間 滋、高橋 威
Motoi SASAGAWA,Mariko KIKUCHI,Michihito ENDO,Shigeru HONMA and Takeshi TAKAHASHI
卵巣癌はヒト固形癌の中では比較的抗癌剤感受性が高く,手術とともに抗癌化学療法が有効な治療手段となっている。術後の寛解導入あるいは補助化学療法として,シスプラチンを中心とした多剤併用療法が用いられる。これにより,以前に比べ化学療法奏効症例数は増加したが,進行症例における長期予後の改善は認められない。長期予後改善をめざして,白金製剤のdose escalation,維持化学療法などが試みられている。また,残存腫瘍径の小さな症例では腹腔内化学療法が有用であり,集学的治療の中で重要な位置付けがされつつある。
近年,パクリタキセル,カンプトテシン誘導体などの新薬が開発されている。卵巣癌にも応用が可能であり,長期予後の改善に,再燃/再発例に対するsecond line chemotherapyとして期待されている。
骨軟部肉腫に対する化学療法の現状
Chemotherapy for Malignant Musculoskeletal Tumors
守田哲郎
Tetsuro MORITA
骨軟部肉腫は種類が多く病態や組織形態は多彩であり,系統的に化学療法が施行されるのは骨肉腫,骨悪性線維性組織球腫,ユーィング肉腫,横紋筋肉腫である。本論文では骨軟部肉腫のうち最も化学療法の頻度の高い骨肉腫の化学療法の歴史と現況,および当科での治療実績について述べる。化学療法の確立前には骨肉腫の累積5年生存率は5〜10%前後と非常に悪かった。その後,外科的治療の補助的療法として術前および術後の化学療法を組み合わせた多剤併用による系統的化学療法が確立され,以後飛躍的に治療成績が向上した。当科で骨肉腫に対する系統的化学療法を開始した昭和52年以降の骨肉腫治療例35例(M1症例2例を含む)の5年及び10年累積生存率はともに59.9%と著明な改善を認めた。さらに治療成績の向上にともない手術法は患肢切断から温存に変わり,QOLも改善した。しかし35例中1例に治療開始6年後に化療によると考えられる二次性白血病を生じた。現在骨肉腫に対する化学療法は多剤併用が一般的であるが,使用薬剤や投与法について今後さらに検討を要する。
乳癌の補助化学療法
Chemo‐endocrine therapy for Breast Cancer
佐野宗明、牧野春彦、張 高明
Muneaki SANO,Haruhiko MAKINO and Takaaki CHOU
乳癌は化学療法に比較的有効であり,ホルモン療法も同程度の有効率を持つ。現在,再発治療は延命効果の域を出ず,根治を目指すためには微小転移を標的とする術後補助療法が必要である。最近,CMF療法が使用可能となったこと,ホルモン療法剤が一通り出揃ったことより,術後補助療法の戦略は一気に拡がった。乳癌は比較的早期から転移をするため全身病と言われ,初期例においても再発例が多いため術後補助療法が推奨されている。しかし,初期例であればあるほど再発しない頻度が高く,危険群の抽出が今後の重要課題である。リンパ節の転移個数が最も強い予後予測因子であり,当科ではこれにより治療方針を立てている。ホルモン療法は化学療法より副作用が少なく,ホルモン感受性がある症例に限られるが初回治療として閉経前後に分けて治療計画がなされる。また,これらの薬剤および治療法は信用し得る臨床試験の結果に従って選択されるべきである。
早期胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の現況
Current Laparoscopic Wedge Resection for Early Gastric Cancer
梨本 篤、土屋嘉昭、秋山修宏
Atsushi NASHIMOTO,Yoshiaki TSUCHIYA and Nobuhiro AKIYAMA
早期胃癌に対しQOL向上を目的に腹腔鏡下胃局所切除術が次第に行われるようになってきている。当科で経験した単発性早期胃癌のリンパ節転移状況を検討した結果,当科での適応は安全域幅を考慮して,(1)隆起性病変では腫瘍長径30mmまで,(2)消化性潰瘍を伴っていない陥凹性病変では腫瘍長径l5mmまでの早期胃癌で,特に胃上,中部前壁の術前深達度診断M癌としている。現在まで胃癌5例,粘膜下腫瘍1例に対しlesion lifting法による腹腔鏡下胃局所切除術を施行した。病変を中央に位置させて切除するのがなかなか難しく,病変が片方に寄るため,切除標本が大きく取れるわりにはsurgical marginが不十分になる傾向があった。全例粘膜内癌,ly0,v0であった。術後は2日目から経口摂取を開始し,創痛も殆どなくQOLは良好であった。術後経過期間はまだ不十分であるが,最長3年9ケ月経過しており,全例再発の兆候なく外来通院中である。
当院における迅速組織診断の現状
Current Status of Rapid Histopathological Diagnosis in Nhgata Cancer Center Hospital
根本啓一、本間慶一、村山 守、渡辺芳明、桜井友子、西村広栄、宇佐見公一、小林由美子、佐藤由美、泉田佳織里、山口栄子、島津ハナ
Keiichi NEMOTO,Keiichi HOMMA,Mamoru Murayama,Yosiaki WATANABE,Tomoko SAKURAI,Kouei NISHIMURA,Kouichi USAMI,Yumiko KOBAYASHI,Yumi SATOU,Kaori IZUMIDA,Eiko YAMAGUCHI and Hana SHIMAZU
当院における迅速組織診断の現状を報告した。件数は毎年400件程度であるが,県内の主要な病院に比較して最も多い。その内訳をみると,以前とは異なった傾向がみられ,迅速組織診断に対する各科の要望も多様となっている。すなわち,単に組織診断を得るためだけでなく,stagingの決定,手術方法の決定のためにも重要な検査となっている。特に近年縮小手術の傾向にあり,断端部の癌の有無の検索は増加している。しかし,検体により迅速組織標本に通常の永久標本と同等の良好な標本の出来を期待することは困難で,そのため診断に苦慮することも多い。病理診断も総合診断であり,より正確な診断のためには,良好な標本を作製することと同時に,適切な臨床情報を得ることが重要である。そのためにも,迅速診断の依頼の際は重要な臨床所見を必ず記載してもらいたい。
大腸内視鏡26年の歩み
Colonoscopic Examination during the Past Twenty-six years
斎藤征史、加藤俊幸、兎澤晴彦、古谷正伸、船越和博、秋山修宏、小越和栄
大腸(結腸と直腸)および終未回腸に発生する病気の診断と治療を兼ね備えた検査法である大腸内視鏡検査は1957年に日本で初めて行われた。当院では1971年に開始され、1996年で26年が経過した。26年間の総検査数は24,091件であり,増え続ける大腸癌と共に検査数急激に増加した。またそれに伴ない手術することなく内視鏡的切除により治癒できた大腸癌(542病変)や前癌病変である大腸ポリープ(腺腫:5,328病変)も多数発見された。しかし,大腸内視鏡に検査に伴う苦痛(挿入痛と腸洗浄)や全大腸挿入の難しさなどにより,上部内視鏡(食道,胃,十二指腸)にくらべ普及率は低かったが,近年大腸内視鏡機器の改良もあり全大腸挿入率は改善(98〜100%)し,検査時問も10分〜20分/人と短縮された。また,検査に伴う重大な合併症(穿孔:0.04%)の頻度は低く,無理な操作をしないことで予防は可能であり,大腸内視鏡は2,000年には死亡率で胃癌を追い抜くといわれている大腸癌の早期発見・治療になくてならない検査であり今後も増え続けるものと思われた。